これまでの内容は語法や構成でしたが、この章からは表現に入ります。
私は細かい点まで気にする性格なので、細かい語法の誤りがとても気になります。これでは書けないのではないかと思うこともあります。
語法などテクニカルな誤りがなくても、表現が乏しい文章は面白くありません。語法をおろそかにしてはいけませんが、後から推敲することも考えて、勇気を持って書こうと思います。
第4日 文章を書くときの心得 上級編
文章を書くときにあまり意識していなかった表現が多くあり、学びの多い章でした。
ひらがなや大和言葉、カタカナの外来語の使い方や避けるべきありふれた表現など、非常に実践的な内容でした。小説を書くのにも役立ちそうな内容です。ブログ記事を書く人にとっても、有益な内容だと思いました。
この章を学習して、ほとんどの文章は短くなるだろうと思いました。私はこの点には気をつけており、本の名前を本文には書かないようにしています。なぜなら、タイトルに書いてあるからです。
アフィリエイトで本を売ろうと思えば、本の名前を書くべきでしょう。しかし、小説執筆の学習と考えると、SEO対策に重点置くべきではありません。ですから、このブログ「七夕帳」はSEO対策をしていません。
学びのポイント
- 漢字の変換に注意
- ありふれた表現に気をつけよう
- 説明は本当に必要か
- 省略できる言葉
漢字の変換に注意
私はブログの下書きをPCで書いているので、知らない漢字も容易に変換できます。手書きではひらがなで書くような言葉も、意識することなく漢字に変換してしまう傾向があります。
所謂を漢字で書くのは難しいですが、PCやスマホは簡単に変換してくれます。とても便利ですが、硬い印象になります。ブログで重く硬くする必要はないので、ひらがなで書くべきでしょう。
ひらがなで書いたほうがよい例です。
- 敢えて→あえて
- 或いは→あるいは
- 即ち→すなわち
- 若しくは→もしくは
- ~程→~ほど
- の為→のため
漢字とひらがなを使い分けるべき言葉です。
【事⇔こと】
7日で身につく正しい文章の書き方 高橋廣敏 著 P99
(例)全力を尽くして事に当たる必要がある。(具体的な出来事や事件) (例)人生には、苦しいことも楽しいこともある。(抽象的な事柄)
ここまで考えたことはなかったです。私の場合は、かっこつけてるような感じがするので、ひらがなにしておこう。この程度の考えでした。
具体的に特定できる場合には、漢字を使い、抽象的で漠然とした場合には、ひらがなを使うのが、一般的です。
7日で身につく正しい文章の書き方 高橋廣敏 著 P99
学びの気づき
漢字とひらがなの使い分けを考えよう
ありふれた表現に気をつけよう
【NGの例】
7日で身につく正しい文章の書き方 高橋廣敏 著 P104
✕ 試合が終わった。敗者の目には、大粒の涙。スポーツは、筋書きのないドラマだと思う今日この頃である。
確かに陳腐な印象を受けました。「大粒の涙」は使い古された表現だと思うし、「筋書きのないドラマ」は臭いと思いました。「今日この頃」は、「もとい」と同じぐらい、古めかしい印象を与えます。
さすがにこのような文章は書きませんが、使ってしまいそうな表現もいくつかあります。
- 頭を抱える
- がっくりと肩を落とす
- 開いた口がふさがらない
小説でこれらのステレオタイプを使ってしまうと、いかにも語彙が乏しい印象を与えそうです。
学びの気づき
「走馬灯のように」は使わない
説明は本当に必要か
私は伝わるのか不安に感じて、説明しようとしてしまいます。小説でこれをやってしまうと、読み手の楽しみを奪ってしまうのではないかと思っています。
伝えないといけないことと、読み手の想像力に期待する部分の分け方が難しいと感じています。
タイトルやテーマを文章の最初で繰り返す必要はありません。
7日で身につく正しい文章の書き方 高橋廣敏 著 P105
私もアフィリエイトブログをやっていたことがあり、キーワードを盛り込む癖がついています。ブロガーは自然に盛り込むと言うのですが、やはりくどい印象は拭えません。
学びの気づき
読み手が既に知っていることはなにかを考える
省略できる言葉
なにげなく使っている「という」「的」「~すること」は省略できます。前から意識していましたが、改めて学習すると整理できました。
「という」には、言い換え、婉曲、伝聞、引用、強調などの意味がありますが、省略しても文章が成立する場合は、省いてもかまわないでしょう。
7日で身につく正しい文章の書き方 高橋廣敏 著 P118
省略できるケースの例も載っていました。
(例)流行というものは、いつか終わるものだ。
7日で身につく正しい文章の書き方 高橋廣敏 著 P118
(例)流行は、いつか終わるものだ。
上手に表現できないのですが、なんとなく「というもの」にニュアンスがあるような気はします。婉曲のような気はするのですが、それほど意味もなく、省略しても文章として成立します。
私は言い切るのが苦手なので、ソフトにしたいと考えてしまいます。その結果、「という」を使ってしまいます。
よく使う表現ですが、すっきりとした説明がありました。
「名詞」+「すること」→省略できることが多い
7日で身につく正しい文章の書き方 高橋廣敏 著 P123
「副詞」+「すること」→省略できないことが多い
このような観点で考えたことはなかったので納得しました。例を読むとよく分かります。
(例)後悔することが、成長につながるとは限らない。
7日で身につく正しい文章の書き方 高橋廣敏 著 P122
(例)後悔が、成長につながるとは限らない。
私は「後悔すること」と書いてしまうと思います。なぜなら、読点の前後の文字数に差があると、視覚的にバランスが悪く感じてしまい、読点の前を長くしたくなります。ですから、「私は」で読点を打つのがとても苦手です。このような誤った感覚を直さないといけないと思っています。
次は省略できない「すること」です。
(例)自然の中でのんびりすることが、いちばん贅沢なことだ。
7日で身につく正しい文章の書き方 高橋廣敏 著 P122
「のんびり」は副詞です。「自然の中でのんびりが」では意味が分からないので、「すること」が必要です。これは分かりやすいと思います。
学びの気づき
文章をすっきり分かりやすくする
学びの気づき【まとめ】
- 漢字とひらがなの使い分けを考えよう
- 「走馬灯のように」は使わない
- 読み手が既に知っていることはなにかを考える
- 文章をすっきり分かりやすくする
漢字とひらがなの使い分けは、注意深く考えようと思います。ひらがなが多すぎると幼稚に見えるので、全体のバランスも考えようと思います。それから、誤変換にも気を付けないといけません。
表現が豊かになるよう訓練することで、使い古された表現を避けられるようになろうと考えています。中には使うケースもあるとは思いますが、厳選したほうがよさそうです。
私は不安から説明したくなるので、冷静に読み手が知っている情報はなにかを考えて書こうと思います。読み手に新しく知ってほしい情報にフォーカスしつつ、すっきり分かりやすい文章が書けるように学習を進めていきます。
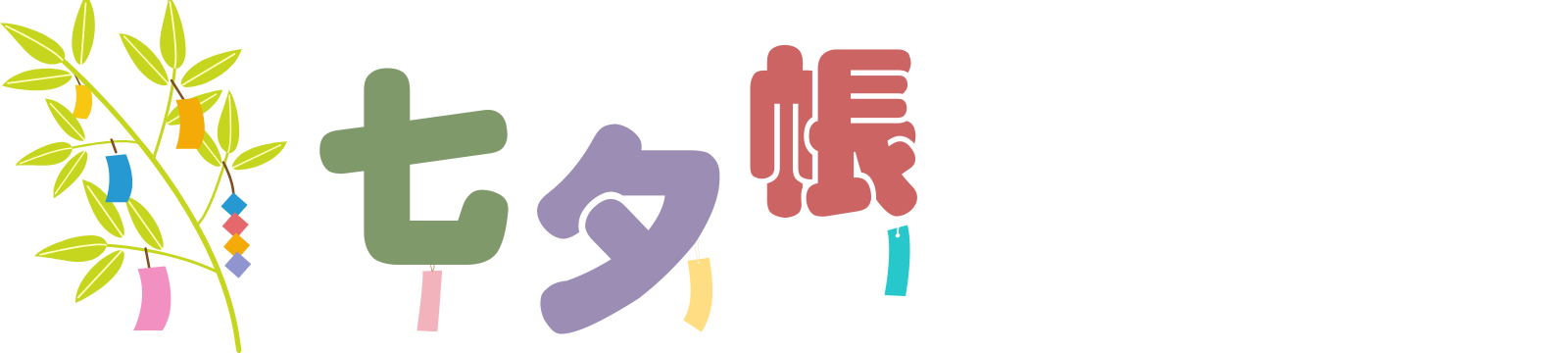
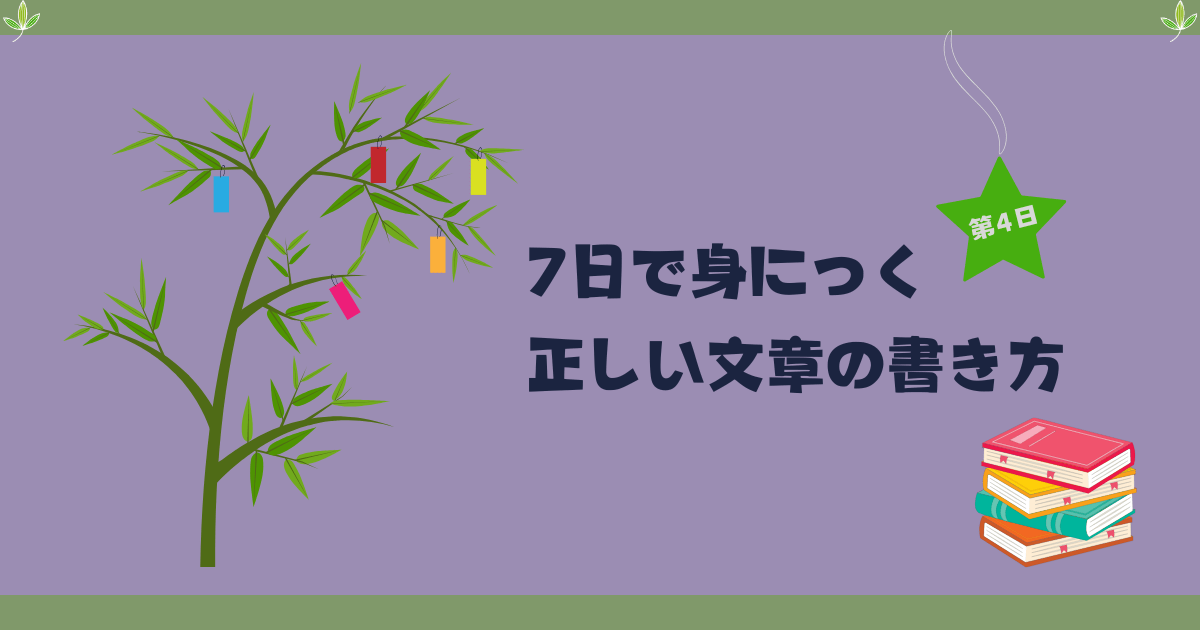
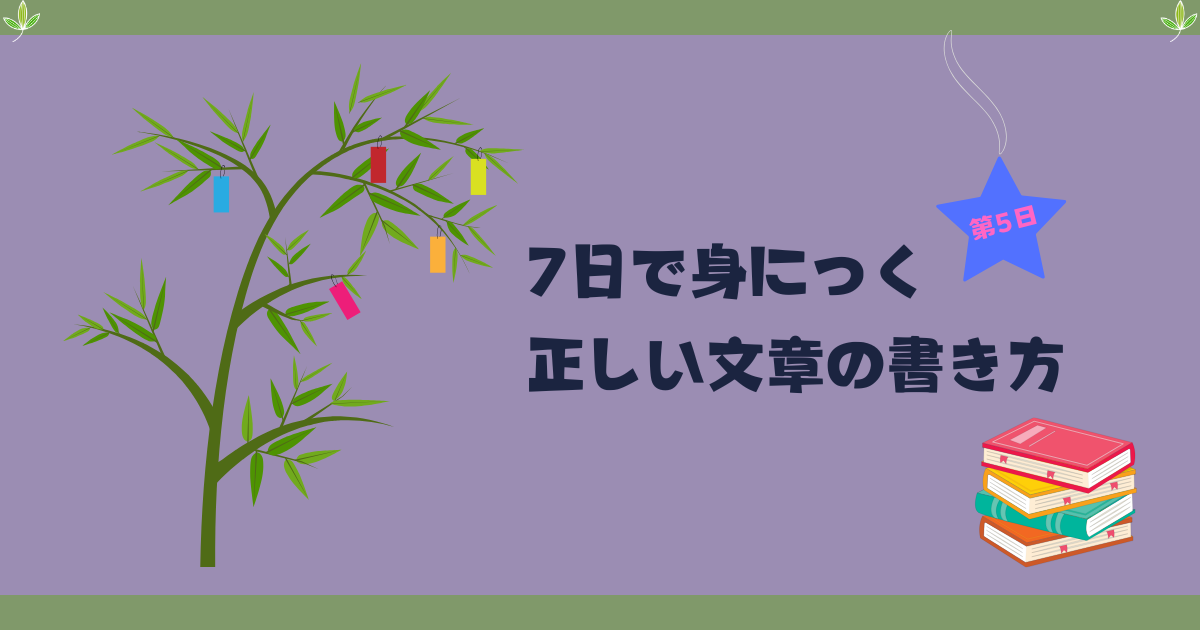
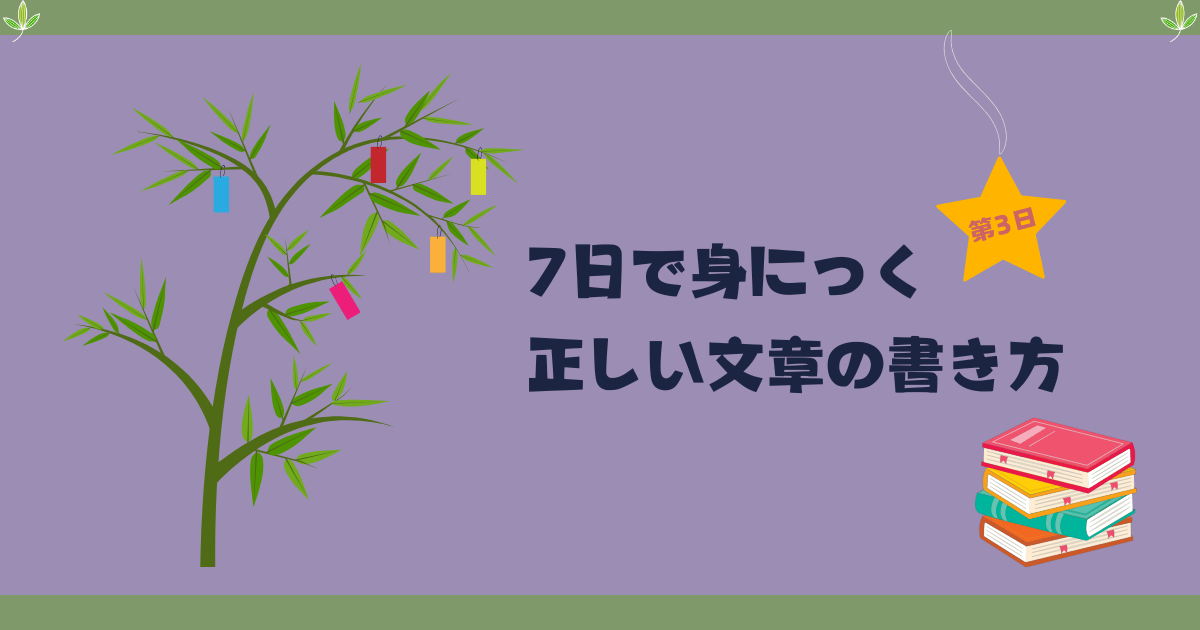
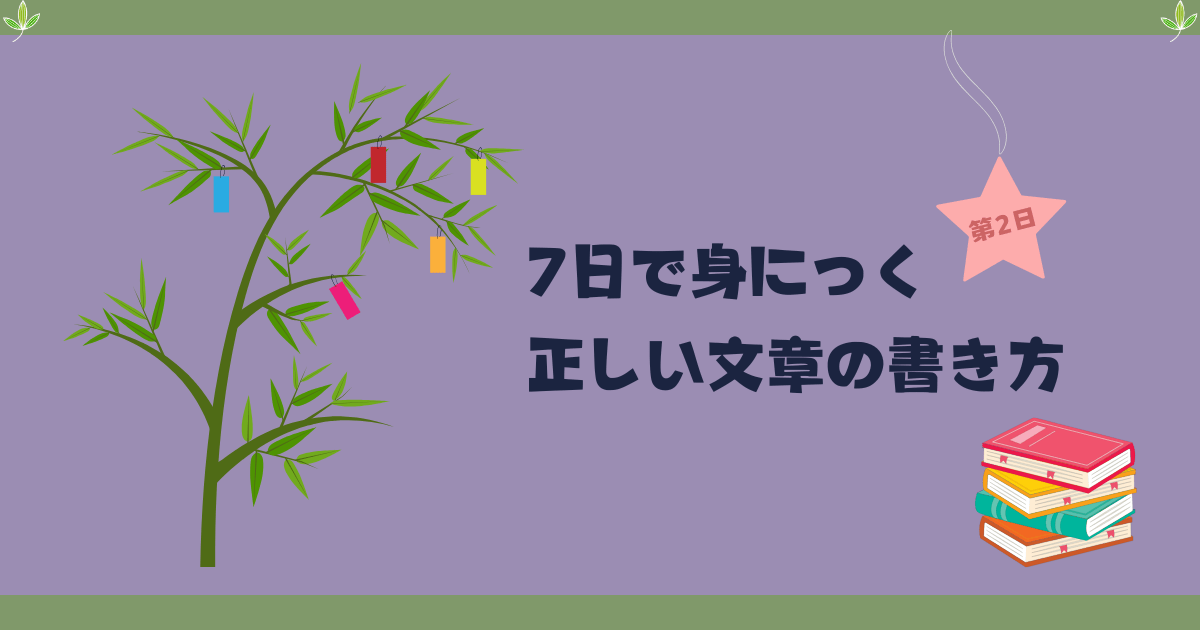
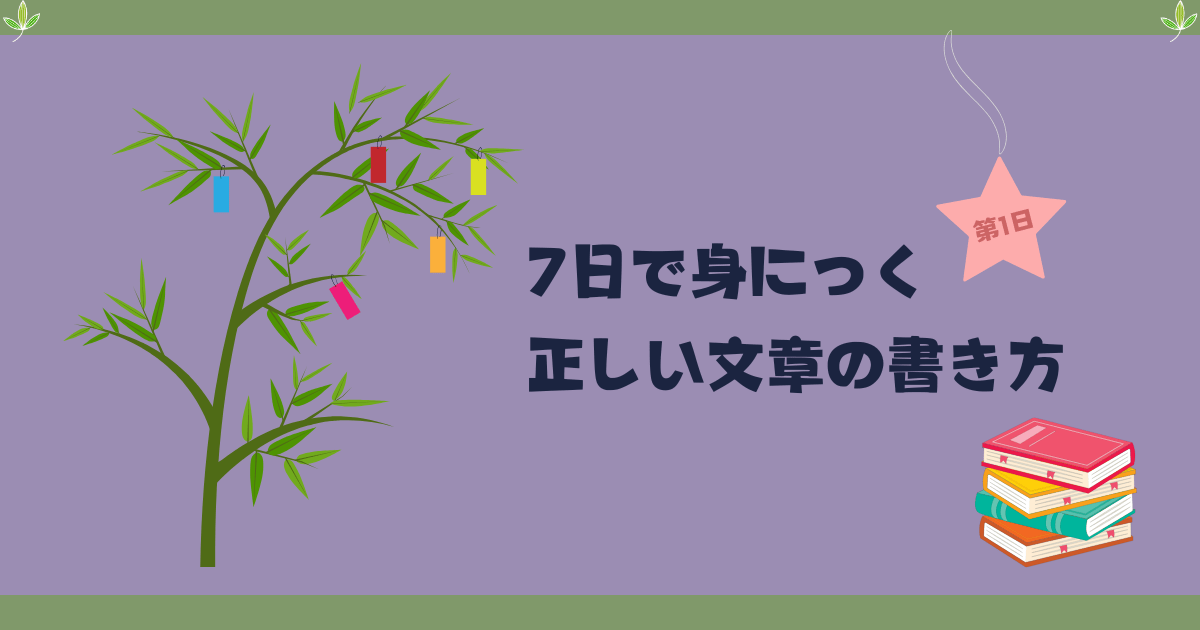
コメント